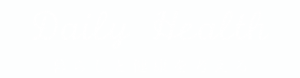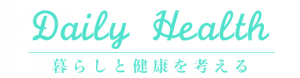カフェインが気になって、コーヒーを避けてしまいがちなあなたへ。
みなさんは、コーヒーを飲まれますか?毎朝欠かさずという人もいれば、中には1日に5から6杯は飲んでしまうという方も^^そう、コーヒーの魅力は私も一度には語りつくせません。^^
そんな私もガブガブ飲める体質ではなく、1日にブラックのコーヒーを2杯飲むと頭がガンガン、なんだか辛い・・・と身体が不調を訴えてきます。本当は好きなんですよ??それでも、なんです。
今回は、そんな方へ朗報をお伝えします⭐️これでカフェインを気にせずコーヒーが飲めちゃいますよ^^早速いってみましょう。
私にとっては衝撃的なニュースから・・・
【カフェイン中毒で死亡例。】
これは海外に限った話ではなく、国内でも報告されているそうです。
出典:YAHOOニュース
上記の記事では、カフェインがもたらす影響として、
「消化管に作用して吐き気がしてきたりとか、心臓に働いてドキドキしたり、本当に中毒症状になると、すごくひどい吐き気と頭痛や動悸が出て最後亡くなるときになると心臓が止まってしまったりそういうことが起こる。」とお医者さんが話されています。やはり量には注意が必要みたいです。
具体的に、どれだけ飲むとやばいのか。
↓
カフェインの致死量。(3グラム)は、コーヒー25杯分にあたる。
いやいや、そんなに1日に飲まないよ!!と思われている方も安心はできません。何もカフェインはコーヒーだけに含まれているものではありません。市販のエナジードリンク。(私の周りの若い子は大好きです。疲れた=コンビニにエナジードリンクを買いに行く。という構図が出来上がっています・・・。)これにもたーーーくさんのカフェインが含まれているんですよ!市販の眠気覚ましの錠剤にも、たっぷり。こういったものを摂るときには、侮らず、しっかりとその量を守ってくださいね!
【ディカフェってご存知ですか?】
なかなか聞きなれない言葉かもしれません。”ディカフェ”とは、特別な製法でコーヒー豆本来の風味はそのままに。カフェインを99%以上除去したのもののことです。(あ、あくまでスターバックスの公式サイトにある定義になります。)
出典:http://www.starbucks.co.jp
どうせ不味いんじゃないの?
なんか、味が薄そう・・・。
そんな意見があっても当然です。ですが、、、
スタバをなめるなよ!!ってことです。結論。^^;(実は元スターバックスのバリスタです。)
いろんな豆のラインナップがありますが、ディカフェであることを抜いてでも、とても好きな味です。ダークローストといって、深煎りの豆。どっしりとしたに残る重厚感。バター風味のペストリーやホイップクリームとも好相性。最高のフードペアリングなんですよ♡^^
【今までは、ディカフェはドリップコーヒーだけでした。】
なので、せっかくスタバに行っても、
スターバックスラテをはじめとして、キャラメルマキアートやカフェモカ、ホワイトモカ、、、こういう類の本当に飲みたいドリンクはディカフェ対応していなかったんです。
今まで、こういうのは全てカフェインが入っているものしか作れなかった。
それが!
それが!!
それが!!!
明日、1/11(水)からすべてのエスプレッソビバレッジもディカフェ対応可能になるんです^^
なんて嬉しい。
実は本当に大きな変化です。これ⭐️
夜眠れなくなるから・・・とコーヒーを諦めていた方、せっかくのスターバックスを楽しめなかった方、もっともっとコーヒーが飲みたいのに、カフェインの量を気にしていた方。明日から解禁です。ぜひ、リラックスタイムを素敵にお過ごしくださいね⭐️
今回は、カフェインが気になって、コーヒーを避けてしまいがちな方でも飲めてしまう”ディカフェ”についてお話しました^^
ココロもカラダもデトックス。すすんで摂りたいデトックス食材はコレ!^^
デトックスとはカラダの「毒出し」と言われていて、身体の中に溜まった老廃物を身体の外へ排出する働きのことを言います。その多くは便で排出され、便が75%、尿として20%、汗として3%、爪・毛髪等で残りの1%が排出される仕組みになっているのだそう。
ココロもカラダも要らないものはしっかり排出して、必要なものを取り込んでいけるようにしていきませんか?今回は、すすんで摂りたいデトックス食材をご紹介していきます^^
【近頃なんだかストレスフル!そんなあなたのためのデトックス食材】
豚肉
豚肉にはビタミンB1(チアミン)が多く含まれていて、疲労回復に効果があることが知られています。皮膚や粘膜の健康を維持する働きもあるので、意外にも口内炎や肌荒れにも効果的なんです。^^
セロリ
苦手だという方も中にはいるかと思いますが、セロリには様々な効果があるんです。ストレス緩和の効果や、血液をサラサラにしてくれる成分、血管の内側をきれいにし、コレステロール値が気になる方にもオススメです。先ほどご紹介の豚肉と一緒に炒めても良いですよ^^私はよく少し濃いめに味付けをして、ご飯に乗せて食べています^^美容にも、健康にも♡
キノコ
この時期おいしいキノコ類。食物繊維が豊富で悪玉菌を減らして善玉菌を増やす役割があるんです。積極的にキノコを料理に取り入れてリラックスするために必要な幸せホルモンセロトニンを増やしましょう!炊き込みご飯に入れると意外に量もたくさんとれてオススメです^^
【利尿作用に効果的があるデトックス食材】
カラダの中の老廃物の20パーセントが尿として排出されることから、ぜひ注目したいのが利尿作用のある食材。ではご紹介しましょう。
バナナ
バナナには多くのカリウムが含まれていて、利尿作用を促します。カリウムはナトリウムを調整する働きをしますので、塩分を摂りすぎることで起こるむくみなどもカリウムが調整し腎臓や副腎を通して排出してくれるんです。
バナナは調理なしで食べられるので、どんなときにも気軽に摂取できるのが良いですよね^^買い忘れた!!なんてときでも、コンビニエンスストアに行けば3本200円くらい、比較的安価で手に入ります⭐️ぜひ、美容のためにもオススメしたい食材です。
ほうれん草
ほうれん草は、水分をしっかり体外に排出してくれるカリウムの他にもカロテン、ビタミンC、鉄分、カルシウムやマグネシウムなどが含まれており、栄養価の高い野菜となっています。βーカロテンは、体内でビタミンAに変化、目に効く!!と昔から親に言われていた所以です。私はサラダとして”サラダほうれん草”を食べることが多いのですが、お浸しなどを作る時には少し注意が必要です。茹でて使うと、ビタミンCが流れ出てしまいやすいので、ぜひ電子加熱をオススメします。さらに、油で炒めるとβーカロテンの吸収率がアップしますので、ほうれん草を使った野菜いためなども良さそうですよ。^^
アボカド
アボカドに含まれるカリウムが利尿作用を促します。また、アボカドにはアーモンドなどに多く含まれる”不飽和脂肪酸”が多く含まれていて、悪玉コレステロールを減らして善玉コレステロールを増やします。血中のコレステロールを調整して皮下脂肪になるのを防いでくれるなんて、素敵すぎます。しかし森のバターと言われるくらい栄養価の高いものですので、そのカロリーには注意が必要です。大きいものだと300キロカロリーほどにもなってしまうということですので、食べ過ぎは注意ですね!!
いかがでしたか?普段はあまり摂っていない!!という食材があったかもしれませんが、これを機に少し意識して摂ってみるのもオススメです^^今回は、すすんで摂りたいデトックス食材をご紹介しました^^♡
そばを食べると身体にいいって本当??
ツルツルと美味しいおそば♡温かくても、冷たくても美味しくいただけるおそばはランチにももってこいですよね^^今回は、そばを食べることで得られる効果についてお話しします^^何の気なく食べるのはもったいなさすぎます!!では早速、いってみましょう♪
【意外と知られていない⭐️そばの持つパワー】
・ダイエット効果
・新陳代謝を上げる
・便秘解消
・病気の予防
・アンチエイジング効果
ざっと挙げるだけでもこれだけの効果が期待できるんです^^♪具体的にみていきますね⭐️
【”そば湯”までしっかりいただきましょう^^】
お蕎麦屋さんで、最後に出される”そばゆ”。日本の方ならまだしも、外国から来られた方にしてみれば”What's?"という感じですよね。^^;そばを茹でるときの”ゆで汁”のことなんです。そば湯までしっかりいただいた方がいい理由、ご紹介していきます。
●そばに含まれる代表的な栄養素:ルチン
ルチンとは、そば特有のポリフェノール。血流を良くする働きや、血管の弾力性を保つ働きがあると言われています。血流を良くしてくれるので、動脈硬化や高血圧の予防に効果的♡
年齢肌が気になる、シミやしわ、たるみの症状にも効果が期待できるので、美肌を目指す女性のオススメ食材だと言えそうです^^
ルチンは水に溶ける性質があるので、そのゆで汁に多く溶け出しています。そばをゆでた、ゆで汁の「そば湯」もぜひ飲むこと⭐️これがポイントです^^♪
●カロリーはともかく、低GI食品です。
低GI食品、という言葉を聞いたことはありますか?美容に敏感な女性なら、知っているかもしれませんね。
低GI食品とは・・・
GIは、Glycemic Index(グリセミック・インデックス)の略で、食後血糖値の上昇度を示す指標のこと。つまり、食品に含まれる糖質の吸収度合いを示し、摂取2時間までに血液中に入る糖質の量を計ったものです。
2003年にWHOから「過体重、肥満、2型糖尿病の発症リスクを、低GI食品が低減させる可能性がある」というレポートが出されるなどの背景から、その後もさまざまな研究が進行し、食品メーカーは食物繊維が多く、エネルギー密度が少ない、GIの低い食品を供給すべきと求めていました。
低GI食品は、現代人に急増しつつある肥満やメタボリックシンドロームの予防・改善の観点からも、注目されているホットは食材なんですね^^
参考出典:大塚製薬ホームページ
各食品の含まれるGI値は以下の通り。
GI値
食パン 91
うどん 85
ご飯 84
パスタ 65
ラーメン 61
そば 54
GI値についての出典:http://rakuyase-diet.jp/archives/10249
つまり、食パンを食べるより、おそばを食べた方が、血糖値の上昇を抑えてくれるので太りにくい。ということがわかっています。コンビニでランチを済ませるにしても、菓子パンを選ぶ同僚を横目で見つつ、自分はちゃっかりおそばを選んじゃいましょう。^^(性格悪い??^^;)
今回は、そばを食べることで得られる効果についてお話ししました^^
美味しいだけじゃない!抹茶のもつ健康効果。
普段からお菓子などでも親しまれている抹茶。実は美味しいだけでなく嬉しい効果があるのはご存知でしょうか。今回は、抹茶がもつ効果についてご紹介していきます。
《 抹茶にはどんな効果があるのでしょうか 》
・リラックス効果(抗ストレス、疲労回復)
・記憶力向上、認知症予防
・美肌効果、ダイエット効果、便秘改善
・月経前症候群(PMS)の緩和、更年期障害予防
・老化防止、抗酸化作用
・高血圧予防、血中コレステロール値の低下
・風邪予防、インフルエンザ予防
ざっと挙げるだけでもこれだけたくさんの効果があると言われています。
《 抹茶のどんな成分がカラダに効いてるのでしょうか? 》
カフェイン
疲労回復効果、脂肪燃焼効果、眠気防止効果があります。ただしカフェインは、摂取しすぎると体に負担がかかるので、一日の摂取量に気をつけることが必要です。
*成人のカフェイン摂取量目安=1日あたり100~300mg
カフェインの量を調べてみましたが、100mlあたりで計算すると、コーヒーには60mg、紅茶はその半分の30mg、抹茶は45mgほどということでした。あくまでも目安として捉えてみてください。
参考:http://coffee.ajca.or.jp
テアニン
頭や身体の緊張を和らげる作用があり、リラックス効果が得られるんだそう。ビタミンCも豊富に含まれているので、ストレスに負けない元気な身体づくりを応援してくれています。テアニンの効果によってα波が増えると、筋肉の緊張が緩んで血管が拡張。血管が拡張することで血流促進、冷え性改善にもつながるのだそう。女性特有の月経前症候群(PMS)の症状の緩和、更年期障害にも。まさに女性に嬉しい効果がたくさんです。
カテキン、フラボノイド
これらは口臭予防に効果を発揮してくれる成分で、サポニン、ビタミンCが含まれており、しみ・くすみの予防に役立つことから、美肌にも効果が期待できそうです。
美容や健康に嬉しい効果が期待できる抹茶。最近イライラしがちの方、お疲れ気味の方、美肌になりたい方まで。うまく生活に取り入れることで、より健康的に美しく♪
今回は、抹茶の隠れた効果をご紹介しました^^
今が旬⭐️食物繊維たっぷりのさつまいもをつかった身体にやさしいプリンをつくってみませんか^^
旬のものを摂ることは美や健康に良いことが知られています。お休みの時間をつかって、からだが喜ぶスイーツをつくってみませんか?かんたんなのにオシャレ^^ギフトとしても喜ばれそうですね⭐️
豆乳のまろやかさ、さつまいもの濃厚なお味がお口いっぱいに広がります・・・^^
今回はyoutubeさんから素敵な動画をいただきました。
ぜひ、みなさんあたたかな良い休日をお過ごしくださいね。
冷やご飯の方がカロリーが少ない??痩せやすいってホントなの?
今回のテーマは、まことしやかに囁かれる都市伝説のようなものなの。
「ご飯を食べるなら、冷やご飯の方が太らない」
皆さんは、どう思いますか??
【私の友人にいるんです。】
冷たいご飯しか食べたくない、って人が。(変わってるーーー>_<)彼いわく、炊きたてのご飯は好きでないようで、冷たいコンビニのおにぎりが一番の好みなんだそう。そう、コンビニのお弁当でさえ温めなかったりするんです。好みは人それぞれと言いますが、変わった人もいるものです^^;
【実はご飯に限らず、炭水化物は冷やした方が太りにくい】
エステ指導者の方に話を聞くことができました^^
「冷やご飯と食べて痩せるかと言われれば、それはウソ。ただし、ご飯を同じ量食べるのだとすれば温かいご飯より、冷たいご飯の方が太りにくいと言えます。」
そーーーなの!!?
「そして、ご飯に限る話ではないんです。ご飯の代わりになる主食といえばパスタやうどんなどの麺類が思い浮かびます。これらの炭水化物にも総じて同じことが言えます。^^」
もう少し調べてみることにしました。
【あったかいご飯と、冷たいご飯。その違いは??】
●炭水化物は二つの栄養素でできています。
1.消化吸収されやすい糖質・・・あたたかいご飯
体内で消化されやすく、すぐに身体のエネルギー源になります。ブドウ糖として血中に送り込まれるので、血糖値の急激な上昇がみられます。
2.消化吸収しづらい食物繊維・・・冷たいご飯
難消化性デンプン(難消化性デキストリンとも呼ばれます。)と呼ばれ、消化吸収されにくい性質があります。糖や脂質の吸収を抑制、太りにくくしてくれます。また、整腸作用、空腹を感じにくくさせてくれる効果なども期待できるのだそう。^^
参考:大塚製薬HP 難消化性デキストリンについて
【結論】
あなたが糖尿病対策やダイエットを考えるのなら冷たいご飯がオススメです^^
糖尿病の方にとっては、その改善に効果的なものばかりです。
・血糖値の上昇を穏やかにする
・食物繊維を補うことができる
・肥満防止につながる
毎日、毎日冷やご飯を食べろ!!というのはとても酷な話。これからの季節なら、冷たくても美味しく食べられるものを日々の生活に意識して取り入れてみてはいかがでしょうか?^^
作ってあげたい彼ごはん3より。^^
コンビニのだとおにぎりや、冷製パスタ、冷やし中華なんか夏に嬉しいメニューずらり並びます。ご自宅でもぜひ、お試しくださいね^^
今回は、冷やご飯の方がカロリーが少ない??痩せやすいってホントなの?をテーマにしてみました^^♡
今日からGWという方も多いかなぁと思います。みなさん、楽しくお過ごしくださいね^^
スタミナUPだけじゃない!!うなぎがアンチエイジングにも良いらしい^^♪
たまにすご〜〜く食べたくなるもののひとつとして”うなぎ”があります^^何だかお疲れ気味の時のチャージアップとしてはもちろんですが、実はうなぎには女性に嬉しい効果もたっぷり♡今回は、そんな”うなぎ”を取り上げます!!^^
【気になるカロリー!でも、実は・・・?】
スタミナアップで知られる鰻。もちろんそのカロリーも高いんだと信じて疑わない方も多いのではないでしょうか?これはイメージが先行してのものであって、丼物であっても、カツ丼が850kcal、中華丼が700kcal、牛丼は680kcal、ネギトロ丼が700kcal、親子丼が650kcalで、うな丼が640kcalであることを比較すると実は低カロリーだということを知っていただけるかと思います。イメージって怖いですよね。私も今まで知りませんでした。丼もののご飯の量は一般にお茶碗1.5杯分とも言われていますので、少し減らして糖質をカットするのもオススメです。
【良質な油を摂りたい方に^^】
最近、魚油というものが注目されています。褐色脂肪細胞と言って、自分の体脂肪をエネルギーに変えて消費してくれる細胞があるのですが、これは通常生まれてその後は減る一方で、増えないとされています。そこで注目されているのがベージュ脂肪細胞なるもの。通常の白色脂肪細胞ではなく、褐色脂肪細胞のような役割をしてくれる細胞で、”魚油”を摂ることでその量が増えると研究発表されているものなのです。
ここでご紹介したいのが、うなぎに含まれている脂肪は「良い脂肪」だということ。魚の脂肪に含まれているのは「不飽和脂肪酸」で、悪玉コレステロールの動きを抑制したり、脳の発達を助け老化による衰えを防ぎ、血液をサラサラにするDHA(ドコサヘキサエン酸)や、動脈硬化を予防し脳梗塞や心筋梗塞などの発病を防ぐEPA(エイコサペンタエン酸)がたっぷり含まれているんです。骨も丸ごと食べられる魚って、案外少ないもの。(ちりめんじゃこもそうですよ!)ただ、塩分も気になるので、その分お醤油の量を加減して撮ることが必要だと言えそうです。
【実は女性にとっても嬉しい効果が♡】
女性にみなさん、ぜひすすんで鰻を食べましょう^^♪日頃不足しがちな栄養素。摂ろうとしていても、忙しさにかまけてやっぱり後回しになってしまったり・・・うなぎには女性にうれしいアンチエイジング効果のある栄養素がたっぷりと含まれています。
・ビタミンA
私は最近、これを気にしてます。^^:ビタミンAは、美容液にも配合されている成分で、お肌の新陳代謝をアップさせ、キメ細やかな肌へと導いてくれます。真皮(お肌の表面上)に存在しているコラーゲンやエラスチンにヒアルロン酸をプラスしてくれると言われていて、加齢や紫外線によってダメージを受けた肌のシワ、シミ、たるみの対策、改善にはピッタリなんですよ^^
・ビタミンB1
B1は糖質をエネルギーに変えるのでダイエットには欠かせません!!ビタミンB1不足によってエネルギー代謝が滞った結果、疲労感がでてくることがありますし、不足すると代謝が悪くなるので、肥満につながるとされています。豚肉のヒレ、鰻、焼き海苔、玄米ご飯などにも含まれます。
・ビタミンB2
B2は、新陳代謝を助けて皮膚の健康を守ってくれます。お肌のターンオーバーは約1か月とされています。もちろん、うなぎを食べたからと言って、次の日からお肌ピッカピカ!!ということにはなりませんが、意識して摂ることでお肌の調子も上がってくるでしょう^^
・ビタミンE
これはよく言われますね。鰻にはビタミンEが豊富に含まれています。細胞の酸化を防ぐアンチエイジング効果にも期待ができ、張りめぐるツヤや弾力を取り戻します。
・コラーゲン
鰻の皮には良質なコラーゲンがたっぷり。皮ごと食べることでよりその効果がアップします。美肌作りには欠かせない栄養素となっています^^
【そう、欠点カバーをお忘れなく!!】
美肌に良いとされる鰻ですが、欠点もあるんです。それはビタミンCと食物繊維の量。ぜひこれは違う食物から摂ることをオススメします。一緒に野菜たっぷりのジュースを用意するのも一つの手です。
出典参考:http://www.yamabuki.co.jp/library/health.html
いかがでしたか??お高いので、早々食べられないよ!というのも実際のところですが、たまには♡ということで、食べられるときには、ありがたくその効果を感じたいものですね^^♪
今回は、うなぎを食べることで得られる美容の効果をご紹介しました!!
意外?!クコの実が持つ驚くべき効果。
皆さんは”クコの実”がスーパーフードと言われているのをご存知でしょうか?杏仁豆腐の上にちょんと乗ったり、創作料理のお店に行くとサラダに使われることもある”クコの実”。今回は、そんなクコの実が持つ驚くべき効果をお伝えしていきます。^^
《 クコの実って一体なに? 》
クコの実は、「ゴジベリー」とも呼ばれており、ナス科の果実で、主に中華料理、デザートのアクセント、最近ではサラダなどに色を添えるためにも使われることが多いようです。
中国では古くから薬として取り入れられているほど、栄養価や効果の高い食材であるそう。最近では海外セレブが美容のためにとクコの実を摂取していたりするので、ご存知の女性も多いかもしれません。ですがその効果は、美容のためだけに留まらず、健康の面でもメリットはたくさんあるようですよ。
《 クコの実に含まれる栄養素 》
クコの実には、なんと100種類のビタミンやミネラルが含まれていると言われています。ビタミンC、ビタミンB1、ビタミンB2、リノレン酸、アミノ酸、カルシウム、鉄分などのミネラルや食物繊維など、美容にも健康にも良い成分がたくさん含まれていると言われています。
《 具体的にどんな効果があるのでしょう 》
・アンチエイジング
クコの実でもっとも注目したい成分は、オレンジの100倍とも言われるビタミンCやポリフェノール類(お蕎麦に含まれるルチンやタンニンなど)、カロテノイド類(βカロチン、リコピン、ルテイン)などの、強い抗酸化力を持つ成分が多く含まれているということです。
このような成分は活性酸素を除去し、体の酸化を防いだり、生活習慣病の予防と改善、老化や肌トラブル(シミ・シワ・たるみなど)のアンチエイジングなどに効果的であると言われています。
・女性にやさしい
クコの実に含まれる”βシトステロール”という成分は、女性ホルモンのバランスを整える作用を持つと言われています。女性は男性に比べるとホルモンのバランスが崩れやすいと言われますが、代表的な効果として、PMS(月経前症候群)や、更年期の症状の予防・緩和に効果があるんだそう。イライラや、もやもや、人にはなかなか分かってもらえない心の状態や身体の状態。それらを緩和してくれるなんて、それだけでも女性にとってとても嬉しい効果ですよね。
・痩せやすい体質に
糖質の代謝を促すビタミンB1、脂肪燃焼を促進するビタミンB2が含まれているため、クコの実を摂ると身体の血流が良くなり、新陳代謝がアップすると言われています。新陳代謝が上がると必然的に基礎代謝も上がるので、痩せやすい体質に。^^
・免疫力UP
クコの実に含まれるビタミンCの量は、オレンジの100倍とも言われています。これは血中の白血球の働きを活発にするのを助けるため、風邪やインフルエンザなど、これからの季節に心配な感染症を予防するなど、免疫力を上げる効果があるのだそう。
《 食べる量に注意 》
クコの実はナス科の食材であるため、食べ過ぎると身体を冷やしすぎてしまいます。胃腸の弱い方、妊婦の方、授乳期間中のお母さんにはオススメできません。特にそのような問題のない方でも、はじめはごく少量から。1日の摂取量は20粒ほどにしておきましょう。^^
続けることで、身体もお肌もイキイキと元気になっていきそうですね⭐️
今回は、クコの実が持つ驚くべき効果をご紹介しました。
飲み続ければ1ヵ月でマイナス3kgも夢じゃない!?「ホットトマトジュース」でスルスル痩せる身体づくり。
みなさんはトマトジュースが好きですか?トマトは食べられても、その独特の濃さと舌にまとわりつくようなドロッとした感じが嫌という方も中にはいるのではないでしょうか。そんなトマトジュース、身体にとって良いのはもちろんのこと、美容の面でもとても嬉しい効果があるようなんです。そして今回はそれをさらにあたためた、「ホットトマトジュース」を飲むことで得られる効果効能についてご紹介していきます。
【ホットトマトジュースで痩せるって本当?】
今回ご紹介する「ホットトマトジュースダイエット」は、きれいになりたい、痩せたい、でも、つらい運動はしたくないというわがままな女性に特にオススメのダイエット法。
その名の通り、加熱したトマトジュースを1日1杯飲むだけの、誰でも簡単にできる超シンプルなダイエット法のこと。 「熱を加えると栄養が損なわれるのでは?」なんて心配は無用。野菜たっぷりのミネストローネが良い例ですが、トマトは加熱によってより強いパワーを発揮、脂肪をメラメラ燃やして代謝アップに一役買ってくれています。^^♪
【ホットトマトジュースを飲むことで得られる効果効能】
1.脂肪燃焼
トマトの代表的な栄養素と言えば、リコピン。このリコピン、ついてしまったいらない脂肪を燃やしてエネルギーとして消費し、代謝をアップさせてくれる効果があるんです。熱を加えることでと体への吸収率が4倍にもなるんだそう。
2.むくみ解消
むくみ防止にひと役買ってくれるのが、バナナやココナツに多く含まれるカリウム。カリウムは利尿作用を促進させて、体内の余分な水分を排出してくれる働きがあります。午後になると足がパンパンになる、女性に多いむくみの症状の緩和に役立ちます。
3.便秘解消
トマトに含まれる豊富な食物繊維が、内臓の壁にへばりついた頑固な老廃物を外に押し出して便通を促します。トマトジュースを温めて飲むことで体の芯から温めて、冷え防止に役立ちます。
4.美白効果
意外に知られていないのが、トマトの美白効果。紫外線、睡眠不足、スマートフォンのブルーライト、アルコールなどさまざまな外部の刺激によって活性酸素が体内で増えることで肌が老化していきます。トマトに含まれるリコピンは、この活性酸素に働きかけて、ハリや弾力に満ちた肌へ近づけるアンチエイジング効果が期待できるんです。
5.疲労回復
何だか体がだるい、疲れがなかなか取れないと感じるのは、体内に溜まった乳酸もその原因のひとつとなっています。トマトに豊富に含まれるクエン酸が乳酸を分解、疲れにくい体づくりをサポートしてくれます。また、胃液の分泌を促す働きがあるので、消化不良を助けてくれます。元気がないなぁというときには是非、トマトジュースを⭐️オススメの健康法です^^
【話題のトマトジュースダイエット。どのタイミングですればいい?】
効果を最大に感じたい方は夜眠る前に飲むのがオススメです。トマトに含まれるリコピンには、成長ホルモンの分泌を促す働きがあります。成長ホルモンが活発になる就寝前のタイミングに摂ることでより高いダイエット効果が期待できるんだそう。
【作り方はとっても簡単^^】
マグカップに無塩のトマトジュースを1杯(200ml)を入れて、電子レンジで1分少々加熱するだけ。^^はじめは、ん??と思う方でも、慣れればミネストローネのようなスープ感覚でいただけます。おなかに溜まりますので、小腹が空いた・・・なんてときにも役立ちそう。ポイントは無塩であることです⭐️お塩が入っている方が飲みやすいと感じる方も多いかと思いますが、むくみ解消には不向きです。余分な水分を出したいなら、ぜひ無塩タイプをチョイスして。^^♪
いかがでしたか?
今回は、ホットトマトジュースが叶える健康・美容法をお伝えしました^^
美味しく食べて、美しさと健康をプラス^^ドライフルーツの量り売りが人気です⭐️
どうしても何だか口さみしく食べてしまう”おやつ”。今回は、美しさと健康をプラスしてくれる、ドライフルーツをご紹介します⭐️
どうせ食べるなら、ぜひ食べてキレイになるものを^^♪罪悪感ゼロのおやつの登場です!!
【FAR EAST BAZZARのドライフルーツ】
今回はドライフルーツ専門店”FAR EAST BAZAAR”をご紹介します♡
《 キレイをつくる、ドライフルーツスタンド♡ 》
エジプト西方沙漠の彼方のオアシスや、エーゲ海、赤道直下の南国スリランカから届いたドライフルーツたち⭐️
FAR EASTが世界から運んでくるドライフルーツは一切の農薬、化学肥料を使用していないということ。また、果実本来の甘み、酸味、香り、色を損なわないために砂糖、香料、着色料、二酸化硫黄も一切不使用。安心して食べられるものだけを厳選しているんだそうです⭐️⭐️
出典:http://fareastinc.co.jp
上記HPにはそれぞれのフルーツについて、果実の栽培・収穫のところから多くのストーリーが語られています。
”身体は食べたもので作られている”という言葉通り、自ら選んで、そして摂るということはとても大切ですよね。意識していきたいな、と考えさせられます。
《 オススメをご紹介⭐️ 》
( アラビアンナイト・ミックス ) 税込2,000円
人気の7種類が贅沢に詰まったセットです。お砂糖や農薬を使っていないので美容や健康に気を使われている方への贈りものにオススメ⭐️
商品詳細:
フィグ(いちじく)/60g
グリーンレーズン/41g
デーツ/40g
生クルミ/38g
アップルバナナ/27g
ブラックレーズン/28g
インカベリー/20g
バランスよくミックスされているので、何を買えばいいのかわからない方にもオススメです♡
出典:http://www.fareastbazaar.net
( アンダルシア・オレンジ ) 税込454円/30グラム
アンダルシアの南方 地中海に臨むアルメリアの海岸沿いで眩しい太陽の光をいっぱい浴びたオレンジ。香りが良くて自然のままの甘さがしっかり詰まったバレンシア品種。
( フィグ ) 税込783円/100グラム
フィグとはイチジクのこと。ホテルのバーで、チーズと一緒に出されたり、ヨーグルトに入れたり♡女子人気が特に高いフルーツのひとつです♪
凝縮された甘さと食感はやみつきなる人、続出です♡^^
( アップルバナナ )税込621円/50グラム
私が選んだのはコレ⭐️最近、むくみがちなので、それを解消するためにカリウムの摂取を!と考えてのことでした^^もっちりとした食感に濃厚なバナナのお味。噛めば噛むほど楽しめる♪こんなバナナのドライフルーツは初めてでした⭐️
一般に、バナナのドライフルーツというと”バナナチップ”として販売されているものがほとんど。ただし、その成分を見ると、ココナッツオイルや砂糖が含まれていて、無添加であることはないんですよね。
いかがでしたか?ひと口にドライフルーツと言っても無添加であるものを探すのは至難の技。そんなときは”FAR EAST BAZAAR”にぜひ立ち寄ってみて^^⭐️
今の自分に足りていない栄養は??美と健康を叶えてくれるビューティーストアです♡
今回は、ドライフルーツ専門店”FAR EAST BAZAAR”をご紹介しました!!^^